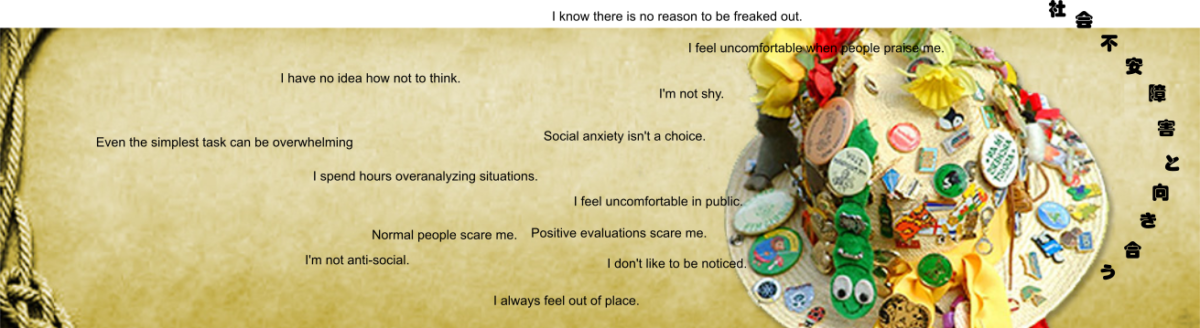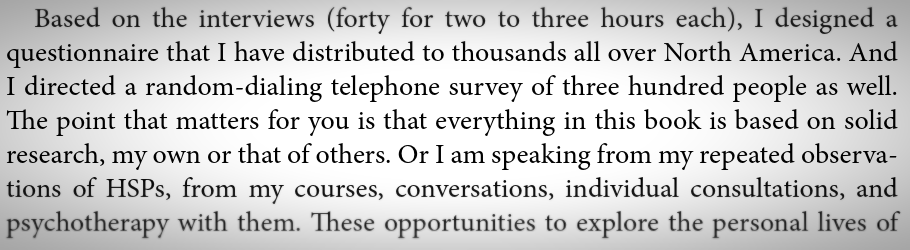前回の記事では、Highly Sensitive Person (HSP)と呼ばれるニューエイジ系アイデンティティ概念が世界的に広まった背景として、提唱した心理学者であるアーロン氏をはじめとする多くの専門家が大々的に一般に宣伝することでHSPブームを仕掛けた経緯があったと指摘した。
今回の記事では、アーロン氏の広めたHSP概念が発達障害や精神疾患を蔑む論調を繰り返すことで当事者や保護者を顧客化する戦略を見ていくために、主にアーロン認定セラピストになるための教科書内容について語るつもりだったのだが、書いていたら大変な量になってしまったので、記事をふたつに分けることにした。
今回はアーロン氏が自らのHSPサイトにおいてASDに対して差別的な発言を繰り返し、当事者からの批判が高まると「私はASDの専門ではなくASDのことはよく知らないんで」と開き直り、発達障害に無知であるにもかかわらずASDとHSPの別診断ができると主張していたという事実を自ら露呈してしまった事件について記述する。 “「愛しているなら自閉症だなんて思わないでしょう」:発達障害や精神疾患に対する差別とHSP概念の関係①” の続きを読む