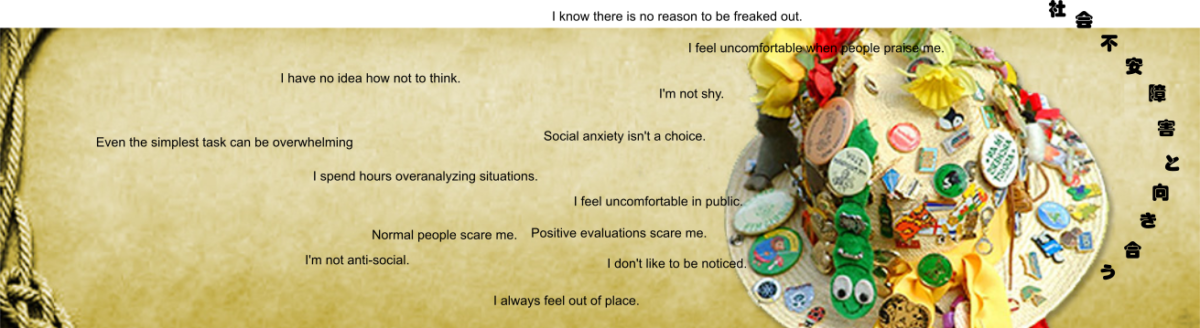プレゼンをすることになった大学の研究者からメールがきた。
似た分野のことをやっていて、前もって個人的に会いたいということだ。了承して会ってみることにした。
その人はスーさんという。
私が以前使ったのと同じフレームワークを使って研究を進めているのだが、うまくいかないと言う。どうしたらよいのか、困り果てているのだが...ということだ。
このフレームワークをある種の研究対象に応用しようとするとうまくいかないのだ。私がやったときも最初うまくいかなかった。それにはフレームワーク自体に問題があり、単純に言うと柔軟性に欠けるのだが、それはフレームワークにちょっとだけ手を加えることで解決できる。
ああ、そのことなら、ここをね、ちょっと広げちゃうんですよ。するとほら、うまくいくでしょ。
やってみせると
「わあっ、できた。これでいこう」とスーさんは大喜び。「このことについて発表してますか。学会とかで」

学会発表...今までずーっと避けてきたからなあ。こんな小さなことでもジャーナルに出せるとは思うけど、それには時間がかかる。書き終えてから査読やらなにやらでひどく時間がかかる。だから学会発表してしまうのが手っ取り早いんだけど、私は社会不安障害でずーっと学会発表だけは避けてきた。
「えっ、じゃあ、この手を加えた方法論については公式に発表してないんですか」
「まったく発表してないんです...」
「困りますよ~。私もその方法でやりたいのに、引用できないじゃないですか。今年中にどこかの国際学会で発表予定がありますか」
「ありますよー」
「あーよかった、それなら使えますね」
ちょっと変わった方法論で研究をやるとき、「同じような方法でOOさんもやったよ」と引用すると、研究の世界では、その方法論に対する信頼度がなぜか上がることになっている。いや、実際上がらないが、上がるかのごとく扱われる。引用することで方法論についての正当性を主張する手間も省ける。(もちろん引用しないと盗用となってしまうし)
国際学会で発表もしないなんて、本当に役に立たない。勝手に研究して自分ひとりの秘密にしておく。貢献度ゼロ。本当に役立たない。
追記(2016/11/09)
と思っていたが、自動思考が発動していたことにずっと後になって、気づいた。学会で口頭発表をしなくても時間がかかろうとも論文を書けばいい。むしろ論文を出すほうが大切なのだ。