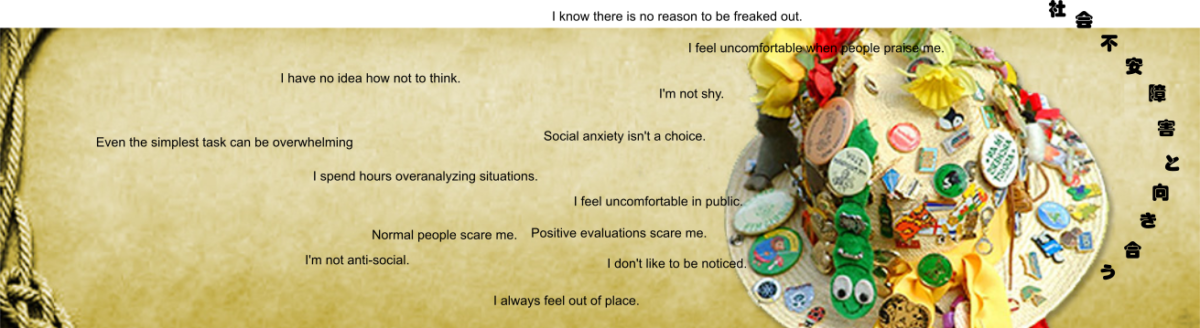「あなたはもう来なくていい」
とセラピストに言われてしまった。
私は認知行動療法のフォローアップを月1~2回受けていた。これは去年半ばに鬱になったので始めたのだった。
楽しく通っていたのに、来なくていいなんて。
「もちろん、あなた自身がセラピーが必要だと感じるなら継続していいと思う。でも今日やってみた不安と鬱のチェックによると、不安の度合いは標準的な人より低くて、鬱は少々強い程度」
なるほど。
「不安については、フォローアップの初日に測ったときすら、高くはなかった」
そうだった。このところ、一年以上の間、様々な不安障害診断尺度を使って自分で測定してみた。常に、標準的な人々より不安が低いという結果が出る。
「あなたはもう不安障害ではない。たぶん、再発することもない」
そうか。そうなのか。
物心つく頃から、ずっと不安障害だったので、私には自分にべったりとくっついたアイデンティティのごとく「私は不安障害である」という感じがあって、「私はもう不安障害ではない」という認識に辿り着けないでいた。
そうだ。私はもう不安障害を患ってはいない。
「むしろ、これからは、併発していた鬱のほうに集中していく方がいいでしょう。これも決して悪い状態ではないので、マインドフルネスの瞑想やリラックス法を日課にしていけば、次第に鬱的なところも軽快してくるはずですから、自分で続けてください。悪化して助けが必要な状態になったりしたら、そのときはすぐに連絡しなさい」
そう言われた。
このセラピー卒業の流れは、前回のジャネットさんのセラピーで経験している。症状が軽減し、クライアントが自分の症状を改善させるのに必要な認知行動療法の技法を自分自身に対して実施できるようになったとセラピストが判断すると、ひとまず卒業させられる。
と言うのは、患者が自らのセラピストとなれること。それがセラピーを受ける際の重要な目標とされているからだ。
この「重要な目標」のことは、ずっとセラピストに言われてきたことだが、これは私自身、ものすごく重要なことだと思うようになった。
セラピストとクライアントの関係がうまく構築され、クライアントはセラピストに心を開く。毎回のセラピーを楽しみにして、セラピーセッションに必ず訪れる。
そこまではよい。
問題は、あまり長期に渡ってセラピーが続く中、クライアントがセラピストに依存状態になってしまう危険が増すところだ。
「あなたとのセラピーなしには生きられない!」 そうなってしまったら、セラピーは失敗に終わったと考えてよい。
ということが昔読んだオーストラリアの新聞記事に書かれていた。セラピーは、クライアントがセラピーなしに元気に生きられることを目標とするものなので、セラピーなしで生きられなくなってしまったら大失敗。そういうことだった。
まあ、その通りだ。
記事はさらにある重要な事実を指摘する。
世の中のセラピストは有能かつプロフェッショナルな人々ばかりではない。中には儲け主義の者もいる。
と言うのは、セラピストはセラピーを施すことで収入を得ているので、クライアントが回復して卒業してしまったら、収入源が減る。お金のことを第一に考えるなら、クライアントが回復しない方が、セラピストにとっては得なのだ。だが、回復させなければクライアントは不満になりセラピーに来てくれなくなるかもしれない。
そこで、クライアントにセラピーが必要であると思い込ませることがビジネス成功のカギとなる。それはセラピストとしては比較的容易なタスクである。クライアントの話をよく聞き、共感を示し、あなたはとてもいい人だと思う...等の褒め言葉を与えれば、精神が不安定なクライアントなのだから、簡単にセラピーに依存するようになる。そうなればしめたもの。クライアントは資金が尽いても、借金をしてでもセラピーを受け続けようとする。セラピストはクライアントに依存し、クライアントはセラピストに依存する。
これをセラピストとクライアントの
共依存関係
と呼ぶ。セラピーを受ける精神疾患患者にとって、たぶん最も気をつけなければならない状況である。
こういうふうになると、セラピストは頑張らない。クライアントの状態が改善しなくても、設定した曝露療法の課題が効果を成していなくても、介入・課題の再設定という適切なステップに進むことなく、延々と同様の課題を続けさせたりする。続ければ、少しずつよくなっていくんだよ、みたいなことを言い続ければ、依存状態になったクライアントは信じる。
これは最悪の状態だ。
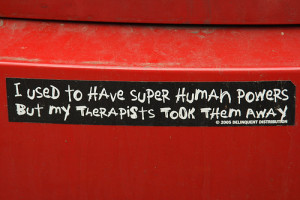
私は自分自身がこれまで知り合ったセラピストがプロフェッショナルな人々であったことを幸運と思うべきであろうが、そこには考え込まれたシステムの影響もあると思っている。
オーストラリアでは、保険適応のセラピーセッションはひとりの患者につき原則として年間10回しか認められていない。
10回ではあるが、実は6回である。と言うのは、6回目のセッション終了後、7~10回目のセラピーを受けたい場合は患者はGP(一般医)へ出向き、新たに書類を作成してもらわなければならない。もちろん、患者がやりたいと言えば、GPは書類を作ってくれる。だが、6回という区切りが存在することで、大抵のセラピストは6回でクライアントを回復させようとする。ものすごく頑張っている様子が私にも分かった。曝露療法の課題などは効果次第で、積極的に介入してくれる。セラピストたちは6回以内で成果を上げるために最善を尽くしているのだ。
ここにセラピストとクライアントの共依存関係が成立する余裕はない。GP、セラピスト、患者の三者が、適切な治療が進行していることを常に確認し合う関係が成立する。
回復しなければ、もちろん10回までやっていい。それでも回復しなければ、再度GPに相談することで、特別にセラピーセッションが受けられる場合がある。だから、患者はこのシステムにおいて決して損をしない。
ついでに、国も損をしない。認知行動療法の個人セッションというものはコストの高いものだが、集中して施行させることで、最小のセッション回数で患者を回復させることができれば、最終的には国にかかる費用は最小限に抑えられるのだ。なんてコスパがいいんだろう!
セラピストも保険適応により、最低でも一時間セッション毎に約125ドル申請できるのだから、悪くはない。皆ハッピーとなるシステムである。
セラピストの教養(学位)レベルとセラピーの質の関係については激しく議論されるものではあるけれど、セラピストの教養レベルは良質のセラピーが実施されることに、さほど関係していないように思う。
Ph.D. を保持するセラピストだって、生活がかかっていれば、クライアントとの共依存関係に陥るだろう。M.A. 保持のセラピストでも、十分な教育を受けていて、その上に全力を尽くすなら、共依存関係を構築する Ph.D. セラピストよりも遥かに優れたセラピーを実施するだろう。
セラピーを医療に活かすシステムの質のほうが、セラピストの学位レベル以上に、実施されるセラピーの質に影響するのではないだろうか。
オーストラリアのシステムで治療を受けてきた私はそんなふうに思う。